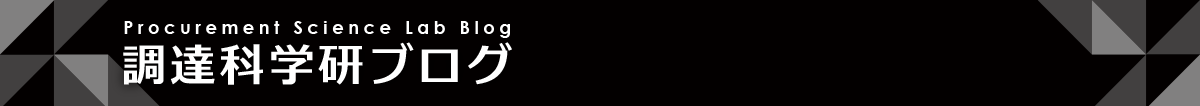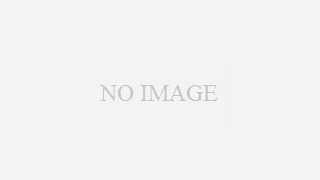 ブログ
ブログ 次世代にツケを残すな
3月3日、経済同友会の岡本(日本生命会長)財政・税制改革委員長は麻生(副総理)財務相に消費増税を骨子とした財政再建提言を行いました。新聞紙上では、①消費税率を2018年度から毎年1%ずつ上げて、最終的には17%にする。②社会保障費は毎年5000億円削減(2014年度で国庫負担が31.1兆円あり、毎年1兆円規模で増加しています)。具体策として、75歳以上の医療費負担を現行の1割から現役所得者並みの3割に上げる、受診時の100円定額負担、高所得者への公的年金等控除の縮小等、③財政健全化法の制定、複数年度予算の導入、独立財政機関の設置等とまとめられています。 年明け1月21日に発行されたこの提言の中身を見てみましょう。標題には「財政再建待ったなし~次世代にツケを残すな~」とあります。そしてこの提言は①ツケを将来世代に回すことなく、法的拘束力のある仕組みをつくる、②財政再建に向けての国民理解の促進、③放漫財政と改革先送りでは破滅的な未来を迎える、④社会保障を「中福祉低負担」から「中福祉中負担」へという4つのポイントを掲げています。 一般に国民の理解という意味で一番浸透しているのは、財務省が先頭...