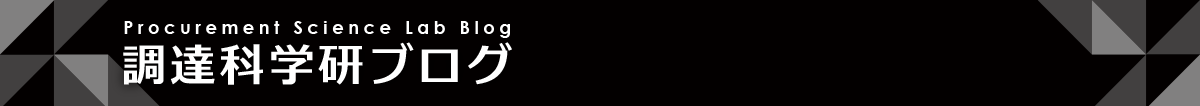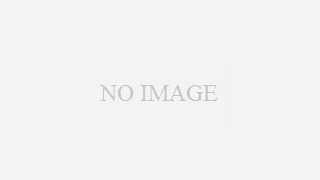 ブログ
ブログ 企業の社会的責任と環境保護
ニールセンが今年第一四半期にインターネットが利用できる世界60か国の各国1000人規模に調査を行ったところ、3年前に比較して45→55%と10ポイント「社会・環境活動に積極的に取り組む企業が提供する製品とサービスをもっと購入したい」と回答しました。私は二つの点でこの調査結果に興味を持ちました。 ひとつはたった3年で10ポイント伸びて、世界中の消費者の半数以上が企業ブランドを社会的責任や環境保護といった視点で見ているということです。もう一点は、この調査を地域別に表すとアジア太平洋(64%)、中南米(63%)、中東・アフリカ(63%)、北米(42%)、欧州(40%)となっていて、環境意識の高い欧州が地域別で見ると最も低く、次いで北米と先進地域は相対的に低い値となっていることです。この結果には正直驚きました。この結果は色々な解釈ができると思いますが、社会環境意識の高い欧州がその経済的停滞によって、以前より意識が低下したと見ることもできるでしょうし、多くの欧米企業がその社会環境意識に対応し、ある種当たり前になってきてしまった結果、それほど大きな選択要因にならなくなってしまったと見ることもできる...