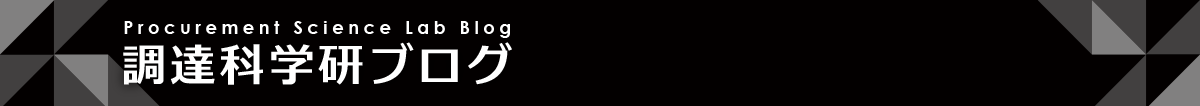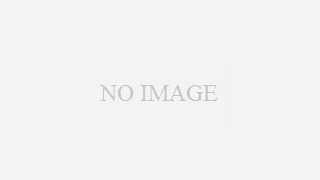 ブログ
ブログ 代議制民主主義からの卒業
米国の人権監視団体「フリーダムハウス」がまとめた2022年の年次報告書によると、民主主義国家の数は2005年の89カ国をピークに減少傾向になり、2021年には83カ国になった一方、参政権や報道の自由などに制限を加えている専制主義国家は、2005年には45カ国だったが、2021年には56カ国にまで拡大したという。1968年に起きたチェコスロバキアでの民主化運動「プラハの春」や、2010年に中東・北アフリカ地域で起きた反政府民衆運動「アラブの春」によって独裁政権を倒した国々もあったが、その後の政情は不安定で混乱しており、民主主義を根付かせることの難しさを痛感させる。 民主主義に関しては、ウインストン・チャーチルが1947年に英国下院で行った演説が有名である。「これまでも多くの政治体制が試みられてきたし、またこれからも過ちと悲哀に満ちたこの世界中で試みられていくだろう。民主主義が完全で賢明であると見せかけることは誰にも出来ない。実際のところ、民主主義は最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが。」 日本の民主主義は、明治維新後の薩長...