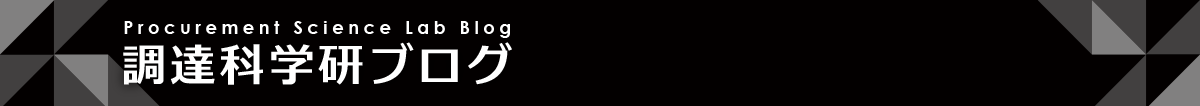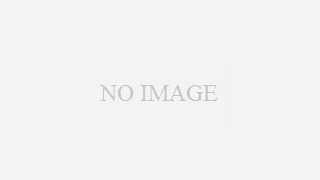 ブログ
ブログ 如来・菩薩・明王・天部
先日、親父の七回忌を終えた。特段、仏教信者ではないし、神道に帰依しているというわけでもない。「普通」の日本人のように無宗教の空間に暮らしている。俗に葬式仏教だとか、正月は神社にお参りするだとか、年末になれば何となくクリスマスを祝う。そういった意味での「普通」の日本人である。海外に行くと、無宗教というのは、一般には信じられない存在で、「特に宗教はないけど」などというとエイリアンのように思われたものだ。それゆえ、キリスト教だとか、ユダヤ教だとか、昨今ではイスラム教がかなり台頭しているので、表面的には勉強もし、スンニ派とシーア派の違いや、なぜに反目しあうのか、偶像破壊をする連中はどういったドグマに侵されているのか等、国際政治の一端を知る上で教養としての知識は身に着けたつもりではいる。 しかし、考えてみれば仏教も色々な宗派があり、何が同じで、何が違うのか、あまりわかっていない。歴史上、宗派間で争ったということも聞いていない。実家の菩提寺は浄土宗であるが、時折、浄土宗だったか、浄土真宗だったか、度忘れする程度の宗教観と実生活においての距離感がある。年をそれなりに取り、神社仏閣に何となくノスタルジ...