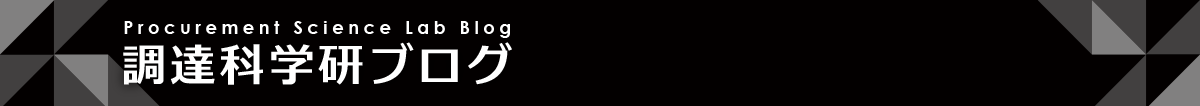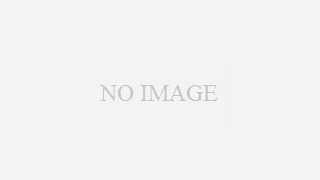 ブログ
ブログ ユーゴスラビア連邦の崩壊
ユーゴスラビアは、かつて南東ヨーロッパのバルカン半島地域に存在した、南スラブ人を主体に合同して成立した国家である。先日、クロアチア、スロヴェニア、ボスニアヘルツェゴビナを回ってきた。風光明媚な地域で観光客に人気なところであるが、四半世紀前には戦禍にまみれていたところである。 私が学生時代には「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字」を持つ多様国家をチトー大統領が一つにまとめて率いた理想社会主義国家と称された。 国家の成立は1918年に遡り、セルビア王国を主体にしてスロベニア人・クロアチア人が集合し、1929年にユーゴスラビア王国に改名され、1945年からは社会主義体制を固めて、ユーゴスラビア連邦人民共和国となった。 チトーは第二次世界大戦後、コミンフォルムの設立者であるスターリンと対立し、社会主義国家でありながら、NATO陣営のギリシャやトルコとの間で集団的自衛権を明記した軍事協定バルカン三国同盟を結んで、NATOと事実上の間接的同盟国となった。 1960年代にはスターリンに代わってソ連指導者となったフルシチョフと和解し、東側からの軍事支援も得た。 そ...