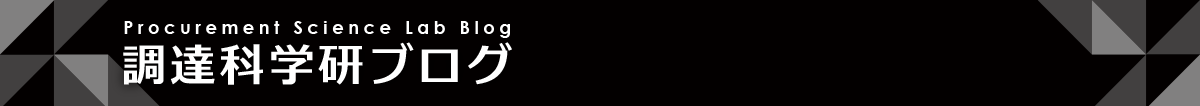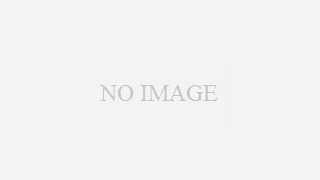 ブログ
ブログ フードサプライチェーン
9月27日の国連本部で振る舞われた昼食は、舌の肥えた世界の首脳らを驚かせるのに十分なものであったろう。 昼食を担当した料理人たちは、現代人の食生活にみられる多大なる無駄が、世界的な気候変動に影響を与えていることの再確認につながることを願い、本来なら廃棄処分されるはずだった材料(ゴミ)のみを使って料理を完成させたのだ。 国連本部で提供されたのは、野菜類の絞りかすを原料とするベジタブルバーガーと、それに添えられた「でんぷん状のトウモロコシから作られた『コーンフライ』」だった。 このメニューを考案した著名な料理人ダン・バーバー氏は、「典型的なアメリカ料理をビーフではなく、牛の餌となるトウモロコシで作った。通常なら捨ててしまうものから、本当においしいものを作り出すことへの挑戦」と語った。 と同時に、今回の昼食会のようなイベントを通じて、食文化が徐々に変わっていくことを期待しているとして「長期的な目標は、残飯から食事を作らないようにすることだ」と食べ物の無駄を削減すべきであるとコメントしている。 国際連合食糧農業機関(FAO)の要請により、スウェーデン食品・生命工学研究機構(Swedish In...