12月12日12時過ぎに電話が鳴った。父の死を知らせる電話だった。満87歳(昭和2年2月2日生まれ)を迎えようという年齢であったし、病院通いをしていた時期もあったので、私としては心の準備をしていた積りであったが、やはりその知らせは「突然」であった。故あって父とは過去20年で一度しか会っていない。最後に会ったのは6年前、生前お世話になった大叔母の葬儀の場であった。父は私が現れることを全く予期していなかったのか、老人性痴呆症からなのか、その場での第一声は「どちら様でしょうか?」であった。さすがに名前を告げると「おぉ、来てくれたか」という返事であったが、父の放蕩にあきれ果てずっと別居していた母に対しても同様の「挨拶」であったことを後日聞いた。そんな父のあっけない最期の知らせであった。
兄夫婦が実家の近くに住んでいて、葬儀の手配を進めてくれていたので、知らせを受けて、取るものも取りあえず「父」が安置された大学病院に向かおうとしていた私は、その日は兄に頼り全てを託すこととして、翌朝の出立とした。葬儀場に着くと大きな和室の部屋で「父」は装束を纏い静かに眠っていた。長年の無沙汰を心で詫びつつも、勝手気儘に、そして自由にかつ無邪気に終えた父の87年の人生に思いを馳せ、そのちょっと痩せた顔に私なりの最期の挨拶をした。
兄の手配により手狭な葬儀場から幾分大きな葬儀場に移ることとなった。葬儀社から手配されたであろう「送り人」が移送前に体を清めてくれるということである。私も映画では見たことがあったが、実際には初めての経験をした。比較的若い感じの男女ふたりが非常に礼儀正しい挨拶の後、手際よく、しかし「父」に十分な敬意を払いその「作業」は淡々と進んだ。小一時間くらい掛かったであろうか。男性によって底の浅いバスタブが持ち込まれ、その上に金属枠のネットが重ねられ、お湯の入ったポリタンクがポンプと手際よく繋がれ、シャワーの準備が整った。その間、女性は「父」の爪を手足10本丁寧に切ってくれる。ひげも丁寧に剃ってくれる。仏への愛おしさすら感じられる一つ一つの作業に私は感動すら覚えた。そして同時に一抹の恥ずかしさを感じざるを得なかった。
いよいよシャワーという段になって、私と兄はそのふたりに手伝いを求められて、4人掛りで「父」を持ち上げネットに乗せた。女性は「父」の頭を腕で抱えるようにして、男性は腰のあたりをしっかり支え、私は肩を、兄は両足首を持ってその手伝いを行った。紛れもなくその男女がその作業の主役で、兄弟は補助者であった。そんなに長い時間ではなかったはずであるが、「父」の皮膚の弾力は生身のそれと変わらないものであったにもかかわらず、その皮膚の温度は想像以上に冷たく、その作業が終わった後もずっとその冷たさが手のひらに残った。
男女はその後もいつもの作業をいつもの通り行っていたのだと思われるが、体だけでなくシャンプーもリンスも丁寧に行ってくれた。洗髪の作業の度に頭部が揺れるので、その反動で、すっと「父」が起き上がってくるような錯覚に囚われた。途中、男性から「最期のご洗髪、なさいますか?」と聞かれ、予期せぬ問い掛けに兄弟ふたりとも躊躇して固まってしまった。生まれてこの方親の髪をシャンプーしたことはない。それら一連の作業はほとけに対しての敬意が最初から最後まで行き届いていた。死化粧の程度や好みは勿論のこと、いつものヘアスタイルはどんな感じですか?と聞かれても私は数十年前のイメージしかなく、上はふんわり目で、横はピッタリ目でと確信の無い返事をするのが精一杯であった。真新しい装束を身にまとい、六文銭の紙シートを入れた肩掛けや三途の川を渡る道中に必要だと思われる木の杖も添えられ、生前おしゃれであった父らしい、「父」の旅支度はひとつの抜かりもなく整った。
移った先のセレモニーホールは「平安会堂」というところであった。私が幼少の時からあったものであるが、当時は「平安閣」という結婚式場であった。兄もここで結婚式を挙げている。係りの人にそんな話をしていると、数年前には改装して葬儀専門の会堂に衣替えをしたということだった。結婚式が減って、葬儀が増えるということなのであろう。ドーナツ化現象を早くから迎えていた私の実家近辺ではまさにそうした社会の変化が起きていた。それを父の死で再確認させられた格好である。この会堂の従業員の方々は訓練が行き届いているのだろう、非常に礼儀正しく丁寧に対応してくれた。宿泊施設も最新の設備が施され、運び込まれた棺が安置されるガラス越しの部屋を除けば、広々としてリゾートホテルと見紛うほどである。後から駆け付けた妹のふたりの娘はその部屋の豪華さに大喜びであった。ひと昔前であれば、一晩中線香や蝋燭の火を絶やさぬよう親族が交代で寝ずに目を配っていたものであるが、今は12時間もつ小振りの蚊取り線香のような線香と、太い蝋燭がその代わりを務めてくれる時代となった。数時間おきに「父」の顔を数十分見ては涙していた7歳下の妹が一番心を込めて父を見送ってくれた。
この会堂の従業員の少なからざる人達は、以前には結婚式を執り行っていたのではないだろうか。だとすればいくら冠婚葬祭と一括りにできるとしても、「喜びのイベント」から「哀しみのイベント」に大きく変わっているのだから、その頭と心の切り替えはとてつもなく大変なことだったに違いない。従業員が総入れ替えになったとは、この地方都市では考えにくい。大手の葬儀社の傘下に入っているのだと思うが、ほとけへの接し方、遺族への配慮、色々な新しい知識を研修において学んでいったのでないか。決まった時間間隔で、礼を逸することなく、ほとけが抱えたドライアイスを交換してくれるその姿に、勝手な想像をした。
人は長い人生の中で転機が必ずやってくるものと思う。変化の流れの速い現代に至っては尚更の事であろう。過去の良き日は良い思い出にするものであって、そこに佇んで、そこに固執して、そこに拘っていては生きていけないと感じる。先輩に教わり、自分流に造り上げ、後輩に教えていく。その中身は変化して当然。変化してこそそこに自分の存在を感じることができるはずである。
行く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず、 よどみに浮かぶ泡沫は、且つ消え、且つ結びて、久しくとどまりたるためしなし、世の中にある人と住家と、またかくの如し(方丈記 鴨長明)。今日という日は、残りの人生の最初の一日と思って2014年を迎える。
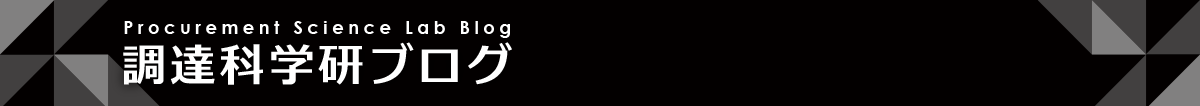

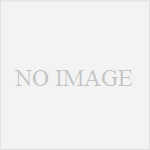
コメント