18世紀から19世紀にかけてイギリスを始めとする欧州諸国で起こった産業革命によって、農業中心の社会から機械化された工業社会への移行が進みました。労働市場においても、機械化と分業化が進み、生産効率が大幅に向上しました。これにより、多くの労働者は単純作業に特化した分業労働が求められるようになりました。
産業革命初期の工場では、労働条件は非常に劣悪で、長時間労働、低賃金、労働環境の悪さなどが問題となりましたが、一方で、産業革命により、工場の管理職や技術者、運送業者、鉄道労働者など新たな職種や産業も生まれました。また、多くの第二次産業においては、産業の発展に伴う需要の増大により大量生産が進み、一定のスキルや知識を持つ均質な労働力が必要とされるようになりました。
そのようなニーズは教育にも影響を与え、基礎的な読み書きや計算などのスキルを習得できる公立学校や普通学校などの基礎教育の普及が進みました。労働者の子供たちにも教育の機会が与えられ、均質な労働力の形成が促進されました。
また、一部の職種では、より高度なスキルや専門知識が求められました。このため、職業教育や専門学校が設立され、労働者が必要な技術や知識を習得する機会が提供されました。職業教育の発展により、労働者の技能レベルが向上し、次々と均質な労働力が形成され、労働者の社会的地位が向上するケースも見られました。教育を受けた労働者は、より高度な仕事や管理職に就く機会が増え、経済的・社会的な成功を収めることができたのです。
産業革命の波が日本に到来したのは、明治時代後半から大正時代にかけてになります。明治政府は教育の普及を図り、国民の教育水準を向上させました。西洋の知識や近代化思想が広まり、産業化への意識が高まりました。日本において独自の進化を遂げたと考えられるのは、勤勉を基礎とした労働倫理でありましょう。その礎は農耕社会にまで遡ることが出来るでしょうが、やはり忠義、礼節、努力といった「武士道」精神にその中核を見出すことができるのではないでしょうか。武士たちは修行や武芸の研鑽を通じて自己の向上を図り、勤勉さを示しました。
加えて、江戸時代に日本社会に広く浸透した儒教の影響も見逃せません。儒教の思想においては、労働倫理や個人の努力による自己啓発が重視され、勤勉な生き方が奨励されました。この影響を受けて、日本の社会では勤勉さが美徳とされるようになりました。
渋沢栄一翁も読んだとされる英サミュエル・スマイルズ著・中村正直訳「西国立志編」は当時ミリオンセラーになるほどの人気本でした。その骨子は「勤勉して心を用うること、および恒久に耐えて業をなすことを論ず」「幇助、すなわち機会を論ず、ならびに芸業を勉修することを論ず」「みずから修むることを論ず、ならびに難易を論ず」といった精神を錬磨し人格を高める、つまり自ら修め養う「修養」の意義が唱えられています。1872年に学制が公布された時には「西国立志編」は教科書としても使用されるようになったほどです。
大正期に入ると「修養」から「教養」が分離独立する形となっていきます。明治時代まで重要とされていた「修養」は、個人の心身の鍛錬や道徳的な教養を指す言葉であり、人間形成の目的として位置づけられていました。大正期になると、「教養」という概念がより注目されるようになっていきます。教育の目標が修養から、広い範囲の知識の獲得や学問的な教養の獲得に焦点が置かれるようになりました。社会の変化や科学技術の進歩に対応するため、多様な知識や教養が必要とされるようになったのです。大正時代には、大学教育の普及も進みました。大学は高度な学問的教養を身につける場として重要視され、学問研究が奨励されました。これにより、教養教育としての学問的な知識の重要性が高く認識されるようになりました。しかし、皆が高等教育を受けることができる時代ではありません。修養と教養は結果として「庶民の修養」と「エリート御用達の教養」に分化していきます。
昭和期に入ると、この二つが再度企業内において合流し、会社で働くことを通じて自分を磨き高めていく「集団での修養」に変容していきます。戦後は会社修養主義に全面展開されていき、営利と修養を合体させていく傾向が顕著になります。家族経営に代表される松下幸之助率いる松下電器、鈴木清一率いるダスキンのスキルトレーニングやマネジメント研修などはその典型と言えるでしょう。多くの日本企業がポテンシャルの高い社員を新卒採用し、企業内教育を施し、企業戦士を作り上げていきました。
そもそもを遡れば、自立的な営みであったはずの修養が、このようにして外部(企業)の仕組みに依存するようになっていったわけです。個々人は能動的に努力しているようで、実は企業に努力させられていたのかもしれません。昨今では社員の中にメンタルな問題を抱え、衰弱しきった人も増えてきたような気がします。果たして「集団での修養」は当初は自分磨きだったのでしょうが、いつからか自分すり減らしに変容してしまった部分もあるのかもしれません。
これまでの文章は随分ChatGPTの助けを借りています。いつもより情熱の薄い文章になっているのを自覚します。我々はまさにAI時代に突入しました。ウォルマートではAIが取引先と2000件を同時に交渉して成果を上げたといったことが報道されました。これまで企業が追求してきた「効率化」という面では既にシンギュラリティを迎えています。しかしAIは徹底した効率化や合理化を求めるので、リスクの高いチャレンジはしません。絵画や楽曲も作り上げてしまうAIとの比較において、人間に残された領域は「挑戦」であり「自己満足に近い自己啓発」≒「修養」しかないのかもしれません。自己啓発は、個人が能力や知識を向上させ、自己の成長や目標の達成を追求するプロセスです。一方、宗教は個人の霊的な成長や真理の追求、幸福の追求などを目的とする信仰体系です。両者は個人の成長や探求を促進する点で共通しています。宗教的な教えや実践が自己啓発の一部となり、個人の成長や目標達成を支援する役割を果たす場合もあります。また、宗教的な経験や洞察が自己啓発のプロセスにおいて意味や目的を提供することもあるでしょう。自己啓発を遡ると宗教へつながるというのは納得感があり、歴史を振り返っても社会不安が増大すると宗教熱が高まる(神頼み)ことは幾度もあったことです。人類にとっては大いなる「内省の時代」≒原点回帰の「修養の時代」がやってきたようです。
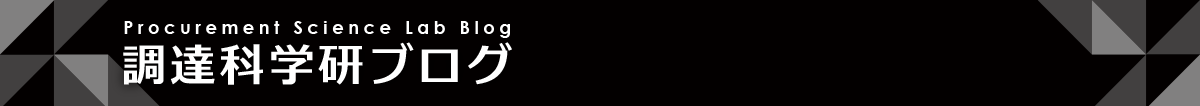

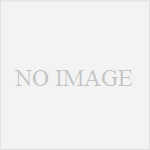
コメント