アイスランドを初めて訪れた。昨年から今年にかけて太陽の活動が盛んなこの時期に肉眼でオーロラを観ることがその目的である。その目的は初日の夜は残念な結果だったが、幸運にも二日目の夜にして早くも達成することができた。しかし同時にかつ意外にも、人間の眼より今やカメラの性能の方が上回っていることを気付かされた日でもあった。これまでも動画静止画問わず、沢山のオーロラ映像を観てきたが、それらはカメラ性能とカメラマンの技術によって創り出された、ある種アーティフィシャルな世界のものであったことに気づかされたということである。
とは言うものの、今回のアイスランド訪問によって新たな気づきも多くあり、大変有意義な旅であった。日本とアイスランドには多くの共通点がある。両国とも火山大国であり、温泉文化が発展している。世界最大の露天風呂施設「ブルーラグーン」は世界中からの観光客で賑わっていた。両国とも周囲を海に囲まれており、豊富な水産資源の恩恵を受けている。捕鯨に関する考え方や取り組みも共通している(アイスランドは1992年IWC国際捕鯨委員会を脱退、2002年に復帰、2006年商業捕鯨再開。日本は長きに渡って科学事実に基づいて自国の主張をしてきたが、2019年IWC脱退)。両国とも国民の教育水準が高く、治安も良い。アイスランド語に初めて接したが、日本語と同様に独自性が強く、日本人が文字列を追ってもとてもまともに発音はできないし、意味も分からない。ともに習得困難な言語の範疇にある。
一方、大いに異なる点としては日本の人口1億2400万人に対してアイスランドは38万人と小国である(面積は韓国と同程度)。両国とも地熱発電に力を入れているが、アイスランドは再生エネルギー100%、うち地熱発電が30%を占める。日本は全エネルギーに対する地熱発電は0.3%に過ぎないので、アイスランドを見習うべきとの言もあるが、発電容量そのものは決して劣っているものではない(率と量を混同させる環境論者のレトリック)。漁業と観光業が中心のアイスランドと工業立国日本とでは経済規模や必要とするエネルギー量は圧倒的に異なる。アイスランドはNATOに加盟しているが、常備軍を持たない唯一の国である。あるのは軽装備の沿岸警備隊のみで2006年に米軍は撤収。その後はアメリカとの防衛保障協定に依存している(NATOに加盟できないウクライナの現下の状況や、トランプ大統領のグリーンランド獲得発言を聞くにつけ、少なからず不安はあるのではなかろうか。ちなみにアイスランドとグリーンランドの距離は290㎞で東京大阪間400㎞より近い)。「ジェンダーの格差に関する調査」ではアイスランドは15年連続1位。世界で最も男女平等が実現されている国と言われている。日本は146か国中118位(2024)。日本の順位が低いのは様々な理由があるが、私見としてはまず女性の社会進出を後押しするために、配偶者控除を無くすべきと思う(多くの反対が出るのは承知しているが)。
これまで述べてきたように色々と深堀するに興味深い論点が多々あるが、今回はアイスランドの歴史をなぞりながら、現代に通じる課題について論じてみたい。
アイスランドの始まりは874年ヴァイキングの入植によるとされている。アメリカ大陸はコロンブスによって1492年に発見されたということが我々の常識になっているが、その500年も前にヴァイキングがアメリカ大陸に上陸していたと北欧では信じられている(アイスランド人の探検家レイフ・エリクソンの銅像あり)。
また930年ごろには世界最古の立法議会(アルシング)によって統治されていたが、13世紀にはノルウェーの統治下(植民地)に、16世紀にはスウェーデンの統治下に置かれた。その頃に強制的に導入されたキリスト教ルター派が今も主要な宗教となっている。アイスランドが完全な独立を勝ち取ったのは1944年第二次世界大戦中の国民投票によってである。
私が最も興味を持ったのは、1958年から1976年までにアイスランドとイギリスとの間に起きた「タラ戦争」である。20年近くも、小国アイスランドが大国イギリスを相手に、国際司法裁判所を絡めつつ、第一次から第三次に及ぶ、国交断絶を挟みながらの紛争を繰り広げている。当該漁場の主たる海産物がタラであったためにこの名が付いたが、アイスランドが主張する漁業専管水域における漁業権を主にイギリスと争ったものである。最終的にこの戦争は欧州経済共同体(ECの前身)が仲介に入り、アイスランドの主張が認められ、イギリスは苦杯を味あわされている。この紛争により現在の200海里排他的経済水域(EEZ)が設定されたことを思うと、これもまた日本と浅からぬ縁を感じてしまう。
当時、アイスランドはヨーロッパで最も貧しい国であったが、20世紀初頭から第二・三次産業へ軸足を移していった。1950年には一人あたりGDPで独英仏を追い抜くまでに経済成長を遂げた。金融と不動産にGDPの26%を依存していたアイスランドは2008年のリーマンショックによって大きな影響を受け、債務不履行(デフォルト)となり、全ての銀行が国有化された(マクドナルドが全面撤退したほどである)。危機を招いた「男性型経営」に対する批判も噴出し、ふたりの女性が銀行の新CEOに就任するなど、女性の社会進出を促した面も多々あったと思われる。
一方で自国通貨が安くなったことにより、水産物の輸出が拡大し、経済はすぐに回復した。観光業にも恩恵をもたらし、2017年には通貨防衛のための資本規制を解除、海外投資も再び自由化された。
ツアーのドライバーは25歳の新婚早々の若者であった。10年前までは芋しか食べていなかったとホントかウソかわからないようなことを自嘲気味に語っていたが、こうして帰国後調べてみると当時の少年の実感としてはそういうものがあったのかもしれない。
今やアイスランドは欧州でスイスに次ぐ高物価国で、特にお酒は酒好きをも注文を躊躇させるほど高い(レストランで頼むとビール1500円、ワイン2000円くらい)。調べてみると北欧諸国は酒害に厳しく、アイスランドでも1915年に国民投票で禁酒法が成立している。ビールは度数制限が課されていて、解禁になったのは1989年と割と最近のことである。酒もタバコも販売は政府直営で、消費税25%に加えて、アルコール度数に応じた高い酒税が掛けられる。空港の免税店では350mlビール6缶で1500円ほどだが、一旦入国すると1缶で1200円はする。NUMBEO(Living Cost)で調べてみると生活費は4人家族で月80万円(賃貸料除く)で日本より81.9%高いと出てくる。さらに賃貸料は日本より205.2%高い。世帯所得の平均が年770万円(日本の子育て世帯収入とほぼ同じ)ということなので、一般の人の生活は決して裕福とは言い難い。スイスは高物価とは言え、隣国と地続きなので、物価の安い国で買い物ができるが、アイスランドは孤島でそれも容易ではない。
世界で安心して水道水が飲める国は12か国あり、日本もアイスランドもその中に入っている。アイスランドの氷河がとけた水を飲んだ時には、久しぶりに本来の水の美味さを感じることができた。厳しい自然と対峙する国民性は同じ境遇の日本人には非常に親和性の高い国としてアイスランドを認識できた楽しい旅であった。
先日の日経新聞では「日本の所得水準、50年後45位、中位群に後退」との記事が掲載されたが、こうしてアイスランドの歴史を辿ってみると、未来予測はその国民の努力次第でいくらでも覆せるものであると確信する。
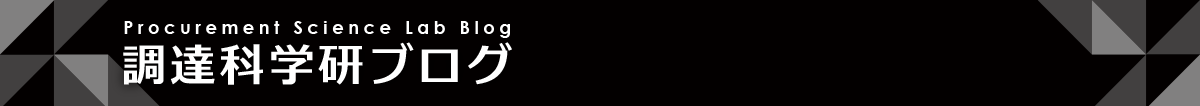

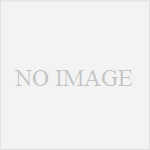
コメント