ナフサは2014年取引相場でドルベースで一番の下落商品となりました。年間で51.1%下げて487ドル/トン(120円/$換算で4万円強/kl)になったと12月27日付け日本経済新聞が報じています。ナフサの原料は原油で、この原油の価格下落(48.4%)が直接的に影響しています。ナフサとは元来ギリシャ語やラテン語で原油を意味する言葉から来ていますが、今では石油精製品のひとつとして定義づけられています。原油を加熱炉で350度まで熱し、蒸留装置によって沸点の低い方から、LPガス、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、重油などのさまざまな石油製品に生まれ変わるわけです。さらにナフサは分解装置等で重さによって軽い方から、エチレン、プロピレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの石油化学製品になっていきます。
ナフサの価格は基本的には原油価格に連動し、その都度都度の為替レートによって換算されます。原油価格は需給によって形成されるとは言うものの、大きくは政治情勢に左右されると言っていいでしょう。70年代半ばまで6000円/klだったナフサの価格は、第四次中東戦争を引き金に発生した第一次オイルショックによって76年には5倍の3万円/kl、そして79年のイラン革命によるイラン石油生産中断を受けた第二次オイルショックによって6万円/klとさらに倍にまで跳ね上がりました。第二次オイルショックが収まった85年から2000年代前半までは15000~3万円/klで落ち着いていたナフサ価格は、BRICsなどの新興国の原油需要増加、産油国の生産能力低下などを背景にしつつも、投機資金や先物市場における思惑買いなどの余剰マネーの流入により08年85000円/klを超える価格に至りました(第三次オイルショック)。2008年9月のリーマンショックで一気に1/3まで価格は落ち込み、その後のアメリカの景気回復にその足取りを合わせるように7万円まで価格を戻してきたのが2014年夏までの推移です。
以降のナフサ価格の下落は7月をピークに一挙に下げ続けた原油価格を反映した形ですが、大きな要因はアメリカのシェールオイルの台頭と言えるでしょう。アメリカがエネルギー輸入国から輸出国へと変身すれば、世界のエネルギー需給に大きな変動要素となります。シェールオイルの製造コストは$70~95/バレルと言われていますが、将来の増産効果によりその半分にまで下がるというシンクタンクの調査もあります。一方、サウジアラビアを盟主とするOPECは昨年末に減産をしないという方針を決定し、それを受けて市場では既に原油価格が$50/バレルを切っています。産油国の採算コストは$40~60/バレルと言われたり、実際の生産コストは償却しきっている設備であれば$10/バレルとも言われています。アメリカのシェールオイルは投資し始めたばかりですから、価格競争になったらOPECなどの産油国には敵いません。それを見越してのOPEC減産見送り判断でしょうか。実際、シェールオイル企業のいくつかは既に破綻してしまいましたし、投資していた日本の大手商社も痛手を被るところも出てきました。
実はもうひとつの要素が「イスラム国」にあります。ご承知のようにイスラム過激派組織がイラクとシリアの一部を実質支配している地域ですが、そこの油井設備を占領下に置き、$40/バレルで市場に流し、戦費を稼ぎ出しているという情報があります。まだ原油価格が下落しそうな兆候が見えるのはそういった背景もありそうです。イスラム国にしてみればタダで手に入れたようなものですから、反イスラム勢力が困ることであれば、手段を選ばず安い原油を市場に流すことはいともたやすいことでしょう。
シェールオイルvsOPEC産油国の構図で、影響を大きく受けているところがロシアなどの歳入を資源に頼っている国々です。採算はどうあれ、国家予算の多くを資源売却代金から得ている国は歳入が大きく減ってしまうと財政危機に見舞われます。ベネズエラやナイジェリアなどはデフォルトになるのではないかと囁かれています。ベネズエラはキューバの原油供給元ですが、キューバとアメリカの国交回復となれば、その大きな輸出先を失い真っ先にデフォルトとなりかねません。産油国の財政運営が健全に行われるための原油価格損益分岐点なるものが英ガーディアン紙に載ったことがあります。ベネズエラは$121/バレル、ナイジェリアは$119/バレル、サウジアラビアでも$93.5/バレルです。サウジアラビアはこれまでの蓄えがあるので、短期間の価格下落であれば問題ない、実は裏でサウジアラビアとアメリカが手を結んで覇権主義ロシアを兵糧攻めにしているといったまことしやかな噂まで飛び出しています。
原油の話が長くなってしまいましたが、ナフサの話で締めくくりましょう。ナフサは国内ではほぼ全量が原油から製造されますが、アメリカでは天然ガス由来のエタンから製造されます。今後の動向によってはシェール革命で米国産のエタンはさらに競争力を増す可能性もあります。また、ポリエチレンなど多くの石油化学製品の基礎原料となるエチレンもナフサから作られますが、中東では原油採掘時の随伴ガスを活用したエチレン、中国では石炭由来のエチレンの生産も進んでいます。
エタンからは製造されないプロピレンのような中間製品もありますが、こうした非ナフサ系エチレンの台頭といった動きもありますので、従来のナフサ価格連動の石油化学製品という固定概念も見方を変える必要がありそうです。技術の進歩は止まることはありませんね。PEST分析の格好の材料になります。
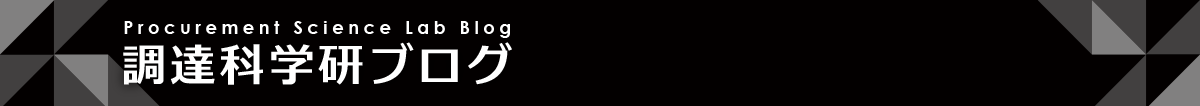

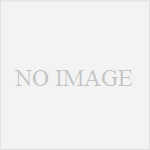
コメント