2012年9月10日NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀 高倉健SP」で紹介された健さんの愛読書をやっと読むことができた。それは健さんが常に持ち歩き、随所に赤線を引っ張り、ボロボロになるまで何度も読み返したという「男としての人生――山本周五郎のヒーローたち」(木村久邇典著、グラフ社)という本である。当時アマゾンで調べたら書籍は絶版、中古品は7万円もしていた。そんなに人気があるなら再版されるだろうと高を括っていたが、今日までその動きはない。今やアマゾンにさえ出品はない。「男としての人生」を改題・新装復刊した「山本周五郎が描いた男たち――さまざまな男の心情 15の物語」という本もあるが、こちらも絶版。ヤフオクで5万円程の値段で出品されている。いずれにせよ再版されないのは不思議でならないが、それを出版社に問い合わせるほどの情熱まではなかった。図書館に予約し1年4か月待って漸く手元に届いた「男たちの人生」であった。私は待ちに待ったその本をあっという間に読了したものの、正直感動するというところまでは至らなかった。
健さんはこの本のどこにそんなに惹かれたのか。内容は、朝日新聞社時代に周五郎の担当記者だった木村久邇典(くにのり)氏が、周五郎の著作の中で出てくる男15人の魅力を解説しているものである。様々な男を題材にしているが、(私の勝手な想像の中での)健さんの生き様と照らし合わせてみると、出来不出来に関わらず「命ある限り、男は最期の最期まで己の最善を尽くす」ということに健さんは惹かれていたのではないか、そんな男として生き抜きたかったのではないかと感じた。周五郎も「ぼくは、あっさり諦めて潔く退く人間よりも、あくまで頑張り通す人間を描きたい。自分に与えられた条件の中で、自己に見切りをつけずに精一杯努力する男。そういう男にぼくは取り組んでいきたい」が持説だったと木村氏は記している。
周五郎は「日本人という国民はよろずにつけて辛抱がたりない。粘り強さに欠けている。諦めが早い。熱し易く冷めやすい。これではいけないね。」と言っている。まるで私自身のことを言われているように思った。周五郎の小説は所謂「髷もの」(時代物)が多い。武士の散り様の象徴が「切腹」である。一筆辞世の句を詠み、泰然自若、微笑すら湛えて潔く死んでいく。周五郎はそれを是としない。私は明らかに「桜の花の散り際の潔さを愛でる」側の人間である。多くの日本人もそれには共感するのではないかと自己防衛してしまう。周五郎に言わせれば、「執念がなければ、何も生まれてこない。小器用な模倣品は作れるかもしれないが、本物を創造することはできない。真の文化というものは、長い風雪に耐えぬき鍛え抜かれた伝統のうえに誕生するものなので、日本人のように表面の現象だけに色目をつかって右往左往するような軽薄な国民性からは、ロクなものが生まれてくるはずがない。」と一刀両断である。周五郎の説に異を唱えるものではないが、私は日本人が粘り強さに欠けているとは思わないし、実際日本のモノづくりに掛ける執念や国際競争力の強さ、そして黄綬褒章に見られるようなその道一筋の職人を認め称える風土も長年維持し続けてきていると感じる。明治・大正・昭和の厳しい時代を生き抜いてきた周五郎からすれば、「辛抱が足りない」のだろうが、幸い「おしん」のような境遇になかった私は、正直腰が引けてしまう。
何かわからぬ違和感を感じざるを得なかった私は、三島由紀夫の最期の死に様を思い起こした。1970年に市ヶ谷駐屯地で自衛隊のクーデター決起を促す演説をしたのち割腹自殺を遂げた壮絶な最期であったが、私の思うところ三島の相克とは日本が長年培ってきた日本・日本人らしさと、戦後のアメリカに押し付けられた急場の民主主義に唯々諾々と面従腹背し、金に目の色を変えて追いかける民衆との落差の間にあったのではないかと思う。
健さんは1931年生まれ。83歳でこの世を去った。終戦の時は14歳(三島はちょうど20歳、木村氏は22歳、周五郎は42歳~周五郎の代表作はほとんど戦後の発刊)。やはり思うに敗戦、そして価値観の大転換というものが、その時代に生きていた人のそれぞれの年齢なりに大きな衝撃を与えたのであろうと思う。これまで良かれとされていたことが真っ向から否定され、それも戦前の価値観を引っ張ってきた人たちの中には、まるで人が変わってしまったかのように新しい価値観にすり寄っていくことが目前に繰り広げられたとすれば、否が応でも何が正しいのか、己は如何に生くべきか、自分は何のために存在しているのか、を三思九思せざるを得なかったであろう。敗戦は長い日本の歴史の中では一時に過ぎない事象ではあるが、その時代に生きた人にとっては、日清・日露戦争の高揚感から満州事変~日中戦争と続く50年に亘る戦時下の末に、常勝日本が太平洋戦争で敗戦した時の物理的・精神的衝撃は私には計り知れない。戦後しか知らない私には三島が感じていたであろう「戦後レジームへの違和感」は感じることはできない。この体験のギャップがこの本への思い入れの差となって現れているのだろうか。
そうは言ってもこの本は相応の魅力を有している。読みながら私がメモした文章は以下の四つである。
–ゆるすということはむずかしいが、もしゆるすとなったら限度はない、-ここまでゆるすが、ここから先はゆるせないということがあれば、それは初めからゆるしてはいないのだ(周五郎「ちょくしょう谷」より)
–汝を愛するごとく汝の隣人を愛せよ(新約聖書より)
–おれは人の苦しむのを見るより、自分で苦しむほうがいい(周五郎「つばくろ」より)
–苦しみ悩みつつ、なお働け、安住を求めるな、人生は巡礼である(ストリンドベリ―)
ちょうど「イスラム国」による日本人拘束・殺害のニュース、そして拘束されていたヨルダンのパイロットがひと月も前に焼殺されていたという報道、さらにヨルダン政府による「イスラム国」への報復宣言が為された(リシャウィ死刑囚の死刑執行)。どの時代に生きても大なり小なり起こる理不尽の中で、人間は希望を持ち、ゆえに苦しみ、悩み、怒り、悲しみ、しかし喜びを得んと生きる。誰しもその生きた時代の影響から逃れることはできない。与えられた時代や境遇の中で、自分で考えて精一杯生きていくしか道はない。母は87歳になる。母の生きた戦前・戦中・戦後の話をまともに聞いたことがなかったことに気が付いた。そして無性にそれを聴きたくなって私は電話を掛けた。
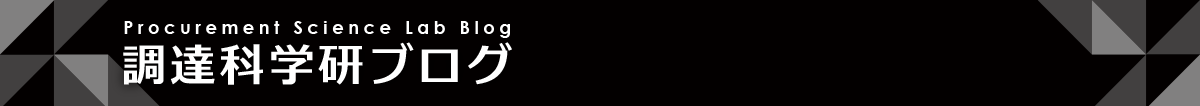

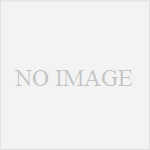
コメント