Concurrent~という言葉はいくつもあるが、製造業に携わっている人であれば、真っ先に思い浮かぶのがConcurrent Engineering(CE)であろう。CEの始まりは1982年にDARPA(Defense Advanced Research Projects Agency/アメリカ国防高等研究計画局)が設計プロセスを向上させる研究をしたことが始まりとされている。開発の初期段階から設計・調達・生産技術・製造・品質管理さらにサプライヤーが参加して最適設計を実現しようという試みである。期待される効果は、リソースの有効活用であり、開発期間の短縮、原価低減などである。CEを日本語に無理に訳せば「同時進行技術活動」となろうか。まれに並列的(parallelly)と解説しているものもあるが、間違いである。ConcurrentもParallelも共に同時進行という意味合いはあるが、parallelではそれぞれが距離を保って交わらない活動になってしまう。これではCEの本質的意味を解していないことになる。
1990年代にはBPR(Business Process Re-engineering)という言葉が世界に広まった。企業活動における組織や業務の流れ・ビジネスルールを見直し、最適化に向けた再設計をしようという試みである。CEにしてもBPRにしても行き過ぎた業務の細分化による部分最適志向の弊害への反省から生まれている。日銭を稼ぐ商売から産業革命を経て工業化時代になると、製造と販売がまず重要になり、分離した。さらに製造から設計が独立し、そこから開発が独立し、生産技術も独立していった経緯がある。調達も品質管理も歴史的には製造から独立した組織である。しかし、大きな組織になり全体の把握が社長でも難しくなってくると、それぞれの組織が自己目的化してしまい、企業の目標や事業の目的とは離れたところで自己の存在意義を正当化することを始めてしまった。それでも企業が成長している間は問題が表面化してくることはなかったが、グローバル競争時代になって顕在化した業界が少なくないであろう。
斯様に個別最適から全体最適へという志向は少なくとも学術的には30年以上もの進展を遂げているが、企業の現場ではまだまだ個別最適の呪縛から解き放たれているとは言い難い状況が続いている。その理由を考えてみると、ひとつは需要>供給ビジネスの発想から抜け出せていない事が挙げられる。業種によってはグローバルでみても需要>供給が継続している分野があろう。ここでは供給者は皆当面生き残れる。強弱はあるであろうが、弱者でもセグメントや地域を絞って存在できる可能性が残っている。しかし、参入障壁が外れ、技術の優位性が崩れ、多くの新規参入企業が現われ、ひとたび需要<供給になった場合には、弱者はひとたまりもない。経済のグローバル化は一方で新興国の需要増というビジネス機会があるものの、何らかの強みがなければ、国境や地域のボーダーを軽々超えて強豪が迫ってくる。需要<供給の状態になったら、圧倒的な量的スケールで市場を制圧コントロールするか、質的変化を遂げて商品やサービスの差別化を図る以外に生き残れない。前者であっても常にカルテルの法制限があって、一企業の思惑通りにはいかない。
歴史を持つ全ての企業は必ず発言力の大きい部署がある。これまで企業を牽引してきた実績と自負を持つ部署である。その企業の強みと言ってよいだろう。しかし、市場が大きく変わると強みが弱みに変わってしまうことも多くの歴史が証明している。どのような組織も一旦、目標が定まると手段が目的化してしまう危険性を孕んでいる。成功体験があればなおのことである。技術革新によって日本経済を支えてきたエンジニアには、自ら何でもやるべきであるという考え方が一部に残っているようである。しかし、エンジニアがやるべき付加価値創造に時間を費やすことができなければ本末転倒である。グローバルに展開しなければならないビジネスは複雑化しており、専門家が連携しながら同時進行形で知恵を出し合い進めていかなければ、質的にも時間的にも競合に出し抜かれてしまう。その結果、企画の練り直しを繰り返し、リソースと資金と時間を無駄に費やし、最悪上市するチャンスを逃してしまう。
Concurrent Management(CM)という言葉は耳慣れている感もあるし、新鮮な感じもする。これに関連する著作を調べてみたところ20年近く前に数冊発刊されていることを知った。その後、その概念は広まることはなかったが、CEのような製品開発における最適化をさらに広げ、その対象を経営全体の最適化、さらにはステークホルダー全てを含めた全体最適を実現しようとする経営手法である。社内的には特にCE活動にMarketingを加え、①どんな製品を(商品企画開発)、②どのような方法で(製造プラン OEM/ODM)、③どのような顧客へ知らしめるかのアプローチや売り方(販売・マーケティング)、④どのような方法で顧客のもとに届けるか(物流・流通・販売)、⑤そして成功の評価(売り上げ、利益、市場シェア)の視点で全社一丸となって取り組むものである。今この概念を古い棚から引っ張り出してきたのは、昨今のICTの発展で各部署の見える化が数十年前に比べて格段に容易になっていると考えるからである。各部署の事実の見える化で、顧客にとって無価値・無意味な社内論争に時間を費やすことを排除できるのではないだろうか。なぜなら共通の事実に基づいて判断できるようになるからである。社内に勝ち負けなどない。あるべきなのは顧客志向のみである。
最近、多くの企業がCommunicationの問題を課題として挙げている。Communicationの問題がない企業はないといっても言い過ぎではないであろう。Communicationの問題の底流には企業文化の影響が必ずある。個人の自主性や創造性を尊重し、生き生きと活躍できる仕組みや組織運営といった風土が言葉だけでなく、実際に現場で根付いているか。トヨタ生産方式にしても、GEのSix Sigmaにしてもひとつのツールを長年かけてしっかり根付かせることで全社の共通基盤を強化し、部署間のCommunicationが図られる風土を作っている。そこには他の企業が形だけ真似ても継続的には成果が出せない企業文化の存在がある。形式やスローガンだけ他から持ってきても、高圧的な会議や、失敗や非難を恐れる会議が続いているようであれば、良いアイデアが出るはずもない。
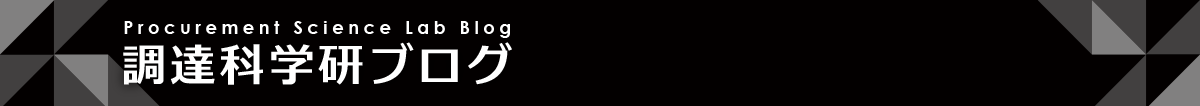

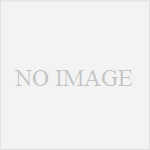
コメント