19世紀は生物学が近代化した時代だと言われている。それまで生命に関しては、他の物質に存在しない超自然的な力を持っているという生気論が支配的であり、基本的には古代ギリシャ時代から変らぬ伝統的意識に宗教的要素が加わり固定化していた。しかし、近世ヨーロッパにおいて18世紀にはあらゆる自然現象が神とは無関係であるという立場を取るディドロ(仏・哲学者)のような学者が現れ、生気論への反論が唯物論者から試みられるようになった。神が創造した「種」が固定的なものではなく、進化によって変化するということを機械論(生気論の反語)的に証明しようとする動きは当時「創世記」への大いなる挑戦であったと言える。
チャールズ・ダーウィンが進化論を唱えた「種の起源」は1859年に出版された。ダーウィンの説は自然淘汰説として有名である。厳しい自然環境が、生物に無目的に起きる変異(突然変異)を選別し、進化に方向性を与えるという説である。この理論は時折ビジネスの場でも引用され、環境に対応できない企業、組織、個人は生き残れないといったような使われ方をされ、一般にも定着している考え方であろう。
この説は適者生存とも呼ばれ、生物の繁殖力は環境収容力(生存可能数の上限)を超えるため、同じ生物種内で生存競争が起き、生存と繁殖に有利な個体が、その性質を多くの子孫に伝え、不利な性質を持った個体の子供は少なくなる。つまりは有利な個体が持つ性質が維持・拡散するというメカニズムである。
19世紀以前は「神の思し召し」としか説明されてこなかった生物の不思議が、ダーウィンにより実際に観察された現象から導き出された自然淘汰説によって、徐々にではあるが、一般に受け入れられるようになっていった。
実はダーウィンの進化論の50年も前、ダーウィンの生まれた1809年にフランスのラマルクという博物学者は「動物哲学」を記し、「用不用説」と呼ばれる進化論を展開している。この説はキリンの首に代表されるように、動物がその生活の中でよく使う器官は次第に発達する。逆に、はじめから存在する器官であっても、その生活の中で使われなければ次第に衰え、機能を失う。つまり個体が後天的に身につけた形質が子孫に遺伝し、進化の推進力になると唱えていた。
ダーウィンとラマルクの説の最も大きな違いは、前者が進化に方向性はなく偶然の産物であるとするのに対し、後者は生物側に進化の主体性を求めるものである。今では遺伝学が発展してDNAによる遺伝メカニズムが広く知られているが、1865年に発表されたメンデルの「遺伝の根本法則」は当時、世の注目を得ることはなく、その功績が認められるのは彼の死後四半世紀経ってからのことである。それゆえダーウィンもその情報を知ることはなく、自身の理論に遺伝の概念は全く触れられていない。遺伝や突然変異の考え方が一般的になった今でも、先天性と後天性のどちらが優位かという議論は分野ごとに盛んに行われており、従来の学問の垣根を超えて広がりを見せている。
冒頭に少し触れたように、進化論はヨーロッパ人の心に永く受け継がれてきたキリスト教的人間観(神、人間、自然の対置)に真っ向から反するものであった。進化論は当初、生物一般を扱ったものであったが、事が人間に及ぶと、当時の宗教界から激しい反発を受けたのは当然であった。ダーウィン自身は自伝で無神論者であることを公表しているが、まさに進化論も極めて機械論的に論理立てた理論を展開している。
一般の生物界では自然淘汰が正常に機能しているのに対し、人間社会ではヒューマニズムが関わって進化論(自然淘汰)が機能しないので、逆選択(淘汰されるべき人間が淘汰されない)が起こるという考え方も生まれた。つまり、人間社会で自然淘汰が機能しないのであれば、人間は進化するのではなく、退化の一途を辿ることになる。この問題を取り上げ優生学を提唱したのが、ダーウィンの従弟のゴルドンである。この優生学とは人種の劣悪化を防ぐための手法を研究目的としたものである。ゴルドンの主張は、人間に人為選択を適用すればより良い社会ができるというものであったが、のちに民族主義と結合してナチスによるユダヤ民族弾圧という極端な事態を生み出すことに繋がってしまった。
科学の発展は近年、土壌汚染や水質汚濁、オゾン層の破壊など負の側面も見せてきた。世界的な環境対策の意識が広がってきたことは歓迎すべきであるが、必ずしも世界市民全員が諸手を上げて賛成しているわけではない。目先の脅威となっている核兵器や生物破壊兵器に対して人類は有効な策を有してはいない。原発推進派はすっかり少数派になってしまった。科学の発展によって冒頭の生気論は近代ほぼかき消されてしまったが、生命現象がもつ全体調和能力をネオヴァイタリズムと称した新生気論も現代生物学では息を吹き返してきている。科学万能時代から時代は確実に揺り戻しがきているように、人間が人間を理解することは機械論と生気論の狭間で暫くは揺れ動き、容易に到達できる領域ではなさそうである。筆者はどちらかといえば「気」の存在を否定しえない生気論者側に立つもので、機械論では割り切りたくない派である。
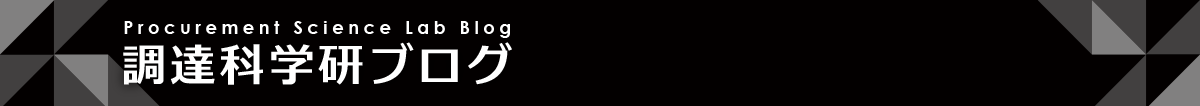

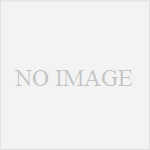
コメント