12月6日、最高裁大法廷は放送法64条1項に定めるNHK受信契約義務付けを合憲と判断した。その趣旨は下記の通りである。
1)特定の個人や団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう、受信設備を設置してNHKの放送を受信できる者に広く公平に負担を求めることは、国民の知る権利を充足する目的にかない合理的であり、憲法上許容される立法裁量の範囲である
2)受信契約の締結はNHKからの一方的な申し込みによって成立するものではなく、双方の合意によって成立し、設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は、判決の確定によって受信契約が成立する
3)受信契約を締結した者は受信設備を設置した月から受信料を支払わなければならないとする規約は、設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的である
これらが15人の裁判官の結論である。木内道祥裁判官のみが、64条1項は判決を求める性質のものではないし、遡及適用や設備を廃止した人への適切な対応は不可能であるという反対意見を述べている。
いずれにせよ、NHKの受信契約義務付けは私法の大原則である「契約自由の原則」より優先するという判決を下したのである。
契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約(私法)は、公の秩序に反しない限り、国家はこれにできるだけ干渉すべきでなく、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のことであり、以下4つに分類される。
1)締結自由の原則
契約を結ぶかどうかを当事者は自分自身で決定することができる
2)相手方自由の原則
誰と契約をするかという意思決定の自由
3)内容自由の原則
契約の中身に何を盛り込むかは自由である
4)方法自由の原則
契約は当事者の合意だけで成立し、書面化するのか、口頭だけかも自由ということ
一方で、強行法規というものがあり、民法90条(公序良俗)公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、当事者間の合意の如何を問わずに無効とする等が、代表的なものである。公共保護を目的とした規定は強行法規となり、独占禁止法、下請法、労働基準法、不正競争防止法、消費者契約法等がある。
つまり、今回の最高裁の判決は、放送法が公共の福祉に適合しているとして、契約自由の原則より優先すると司法が判断したことになる。
放送法は、総則で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を目的として、1)公安及び善良な風俗を害しないこと、2)政治的に公平であること、3)報道は事実をまげないですること、4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることの4つを第4条で定めている。しかし、その実態は、公共放送であるNHKも民法も、全ての局において疑問符をつけざるを得ない状況があるのではないか。一方的な発言を長々と流し、世論誘導を図っている放送番組があるのは事実で、偏向報道との指摘もある。BPOというNHKと民放連によって設置された第三者機関もあるが、その視点は「放送における言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため」であり、自らの信念で放送する番組の作り手に中立を求めるものではない。
先の総務大臣高市早苗氏は昨年、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に電波停止を命じる可能性に言及しメディアから総反撃を食らった。メディアが表現の自由を理由に反発するのはその立場から言って当然であろう。しかし、放送法は不偏不党や政治的公平性を求めているが、この二つは果たして両立するものであろうか。公共放送であれ、民放であれ、事実、真実のみを電波で流すにしても、編集という作業が入る。主張・強調したいところを切り取って放送すれば、人間である以上、程度の差こそあれ、必ず偏る。これは意見が違う人が世の中にいる以上、不可避のことであり、それこそが民主主義の証である。スポンサー収入に依存する民法は、スポンサーにおもねる番組もあろうが、一方NHKは放送法を盾にして、一般視聴者がサイレントマジョリティであることに胡坐をかいて、公共の福祉とは到底言えない領域に業態を拡大していると言えないだろうか(1982年に放送法が改正されてNHKは営利事業への出資が認められるようになった)。
NHK・EテレやNHKスペシャルなど、さすが公共放送といった番組もあるが、私見で言わせていただければ、8割方は公共的なものではない、無くても困らない番組である。
公共の福祉とは何かを再度考えて、必要不可欠なものに絞った上で、月500~1000円程の受信料を徴収し、バラエティ番組や旅番組、グルメ番組など民放でやっている番組は全くやめるか、従業員の雇用を考えるなら、民営化すればいいと思う。
どうせ、中立性は保てないので、思う存分好きな番組作りをして、それらを求める視聴者から堂々と視聴料を取ったらいいと思う。当然スクランブル放送の対象であるから、お金を払わない人は観れないし、電波を垂れ流しておいて視聴料を強制徴収することもない。
現在、電波オークション導入の検討が政府の規制改革推進会議で行われている。導入されれば、既得権に胡坐をかいている放送各社は自由競争にさらされる。電波を購入すれば、誰でも自由に意見を発信できるようになる。それを視聴者が選別すればいいだけの話である。
GHQ占領下の昭和25年に施行された放送法や電波法は技術の進歩、社会の変化から明らかに後れを取っており、時代錯誤の法令になっている。この法令の改革は国会の仕事である。これが票につながるとわかれば、国家議員は必ず動く。選挙で落ちたらただの人。民意を示すことが自由と民主主義を守る唯一の方法である。
契約自由の原則と放送法
 ブログ
ブログ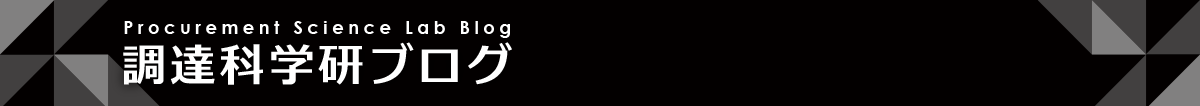
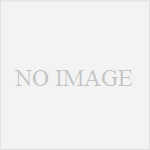
コメント