利子とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価のことである。金融機関などから借りたお金に対しては当たり前のように利子が付く。高度成長の時代には銀行に預けたお金に対しても当たり前のように利息が付いてきたものだが、約20年続いている日銀の超低金利政策導入以来、利息がほとんど付かないのが当たり前になってしまった。平成という時代は平和であったが、低成長の時代でもあった。
日本の利子の歴史を紐解くと、律令体制の時代にコメなど租税として納められないほど困窮した百姓には、神への捧げものとして保管されていた米を貸し与えるということが為されていた。その場合、返す時には借りた米より多い米を神様に返礼するということが行われていたそうで、日本では利子という概念が何らかの形で認識されていたようだ。
ヨーロッパに目を転じると、古代ギリシャの海上交易でも利子を伴う貸付は広く行われていたそうであるが、アリストテレスは「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」(「政治学」1巻10章)と反論している。
宗教的には旧約聖書でも新約聖書でも、利得を期待せずに無償で貸すべきであるという教えが中世キリスト教において重んじられていた。それらに先立つユダヤ教でも、後世のイスラム教でも同胞から利子を取ることは禁じられていた。この「同胞」(あるいは「貧者」含む)という言葉がミソで、たとえばユダヤ人が異邦人であるキリスト教徒からは利子を取ることは禁じられていなかった。15~6世紀頃のヨーロッパでは、「高利の金貸し=ユダヤ人」というイメージが強くありました。ユダヤ教徒は歴史的に苦難の道を歩むことが多かったので、生き残っていく過程で、異教徒にお金を貸すことを正当化していったという経緯がありそうです。その技術を高めていくことによって、今でもユダヤ人が金融業界を牛耳っていると語られます。シェークピアの「ベニスの商人」では皮肉たっぷりにシャイロックという強欲なユダヤ人高利貸しが描かれていることは皆さんもご承知の通りです。
そういったユダヤ人を侮蔑的に表現していたヨーロッパで、実は13世紀くらいからは様々な抜け道を通じて、利子を取っていたようです。カトリック教会は金銭の貸与による金銭の利子を禁じていましたが、事業・土地の賃貸・または土地の果実の販売・その他の資本による利益を否定してはいませんでした。一方、免罪符の発売を行うなど堕落の目立ったカトリック教会に対して反旗を翻したカルヴァンは、労働は卑しいものとする古い宗教観を否定し、労働を正当化することに繋がる「予定説」を提唱します。
「予定説」とは、人が神の救済にあずかれるかどうかはあらかじめ決定されており、この世で善行を積んだかどうかといったことではそれを変えることはできない。教会にいくら寄進をしても救済されるかどうかには全く関係がない。神の意思を個人の意思や行動で左右することはできないという身も蓋もないもので、今では少数派に属する考え方です。
この言説が資本主義の発展に寄与したとする論文が、かの有名なマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」です。カルヴァンの論説は「現世でどう生きようとも救済される者が予め決まっている」というのであるならば、快楽にふけるという対応をする者もありうるはずだ。しかし人々は実際には、「全能の神に救われるように予め定められた人間は、禁欲的に天命(神が定めた職業)を務めて成功する人間のはずである」という読み替えによって、禁欲的労働という倫理を生み出したとします。そして、自分こそ救済されるべき選ばれた人間であるという証しを得るために、寸暇を惜しんで少しでも多くの仕事をしようとし、その結果増えた収入も享楽目的には使わず更なる投資のために使おうとした。そしてそのことが結果的に資本主義を発達させた、という論旨である。その時代のその場所に私は居たわけではないので、すんなりと飲み込める説とは言い難い。
いずれにせよ、そうした道程を経て、資本主義は発達していった。ちなみに初の共産主義国家であったソ連にも利子はありませんでした。道理で効率や納期といった時間感覚がなかったわけです。経済が停滞した理由の一端ではあるでしょう。現代の利子には金銭の時間的価値に加えて、リスクが加味されています。それによって利子率が決まっています。一般に親族・友人間での金銭の貸し借りには利子は登場しません。「ある時払いの催促無し」や「出世払い」「この金は貸すんじゃない、やるよ。返さなくていい」なんていうセリフは今の時代にも生きています。長年の友人同士が金銭の貸し借りがもとで絶交するということもあります。連帯保証人になって一生を棒に振ったという話も聞きます。お金に振り回されることなく、お金と付き合っていきたいものです。
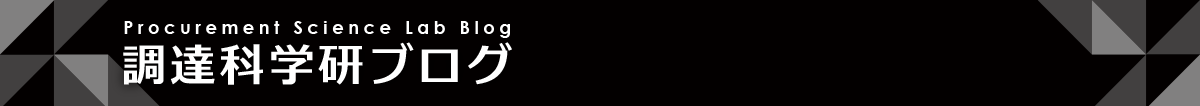

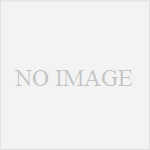
コメント